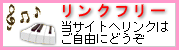ピアノの音がこもったような感じで、よく鳴らないのですが、どうしたら?

- 自宅のアップライトピアノの音がこもったような感じで、よく鳴りません。クラシックの曲を気持ちよく弾けないのです。先日ピアノ調律師の方に見てもらったところ、「こんなものですよ」と言われて、特に改善してもらえませんでした。調律だけはしてもらったのですが不満が残ります。どうしたらよいでしょうか?
音がこもったような感じで、よく鳴らないことについて、ピアノ調律師さんの意見を聞いてみました。
ピアノの音がこもったような感じで、よく鳴らないのですが、どうしたら?
以下、ピアノ調律師さんからのご意見です。
先ずハンマーフェルトが湿度を含んで柔らか過ぎるとモソモソの音になります
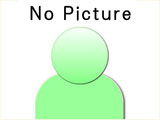
ピアノ調律さん 談
よく鳴らない理由はいろいろありますが、順番にみていきますと、先ずはハンマーフェルトが湿度を含んで柔らか過ぎるとモソモソの音になります。特に雨期は注意が必要です。
次に、アクションの動きが正常かどうか。鍵盤の動き、ウイペンフレンジ、バットフレンジ、ジャック、ダンパーが抵抗なくスムーズに動いているかどうか。
フレンジについてはこれを止めるビスが緩んでいないかどうか。バットプレートのビスも緩んでいないか。
鍵盤の先端のパイロットとウイペンヒールに隙間が空きすぎているかどうか。
鍵盤の深さ、打弦距離、接近、バックチェックが適当な数値に調整されているかどうか。
弦に対し、中央の弦にハンマーの中央が当てっているかどうか。ハンマーが斜めに当たっているかどうか。
2本弦、3本弦に対し、ハンマーフェルトが同時に当たっているかどうか。フェルトの先端の弦跡が極端に深くなっている場合も要注意です。この場合はハンマー整形が必要です。
あとは響板が割れている場合は音に張りがありません。
まだ他に原因があるかも知れませんが、結論として、一度、調律のみでなく、保守点検として、以上の事柄を時間をかけてみていただいては如何でしょうか。
ピアノはk社と思われます、恐らく鍵盤も重くひきずらいのでは?

Music TAKANO
(茨城県水戸市六反田町)
阿久津さん
所持しているピアノはk社と思われます。恐らく鍵盤も重くひきずらいのでは? と思われます。
家は都会ではマンションの低階層で、リビングとキッチンとが同一部屋と思われます。湿気が多くて動きません。
まず疑うべきは、定期的に調律すらやってないと思われますね。根本的には調律では直りませんよ、お金かけるだけ無駄です。
唯一効果的なのは、ダンプチェイサーという器具をつけると、劇的に音とアクションに変化が現れます。
是非購入して装着してくださいね。
ピアノの屋根板にタオルを挟めて、5センチ位開けてみて下さい
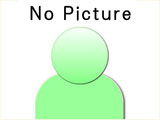
ピアノ調律さん 談
ピアノの屋根板にタオルを挟めて、5センチ位開けてみて下さい。
前方から音が出て、耳元にハッキリ聴こえる様になると思いますのでお試し下さい。
考えられる原因ハンマーとピアノ内部の木部部材の水分密度が増加している状態
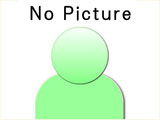
ピアノ調律さん 談
ピアノの音が、こもって伸びのない全体的にボスッボスッっとした音質を改善には、次に上げる方法を試してみてはどうでしょう。
①考えられる原因としましては、ハンマーとピアノ内部の木部部材の含水率が全体的に高く、水分密度が増加している状態だと考えられます。
この状況で打鍵すると、響板はしなやかな震動ができない為に、伸びの無いこもったような音質になります。
故障ではないので、ピアノの近くに湿度計をおいて常時湿度が50%くらいになるように、環境を工夫してみてはどうでしょう……。
②ピアノに鳴り癖を付ける為に、たまには強い音を出してみるのも一考だと思います。
そのピアノは新しいピアノですか、古いピアノですか?

立川ピアノ調律技研
(神奈川県藤沢市本鵠沼)
立川さん
そのピアノは新しいピアノですか、古いピアノですか?
古くて弾き込んだピアノですか、古くてもあまり弾いてないピアノですか?
何だかあまりよく分からないピアノですね。とりあえずハンマー整形からしてみましょうか?
よく鳴らないピアノのは、どこかでエネルギーのロスが生じ、ピアノの響板が十分に鳴っていない状態

株式会社クオルピア
(東京都足立区千住)
倉田さん
こもった音というのはご質問の通り、ピアノがよく鳴っていないのです。
ピアノという楽器は、鍵盤を押し下げるエネルギー(力)が鍵盤・アクション・ハンマーへと伝わり、さらにハンマーの衝突により弦の振動に変わり、そして最終的に弦の振動が響板(ボディー)へと伝わり、響板の振動が空気を振動させて音となっている楽器です。
「よく鳴らないピアノ」というのは、このエネルギーが伝わる経路のどこかで、エネルギーのロスが生じてピアノ(の響板)が十分に鳴っていない状態だと思われます。
逆によく鳴っているピアノ、つまり理想的な状態では、指からの意思(力)が鍵盤・アクション・ハンマーへと伝わり、与えられた弦振動が効率よく響板に伝わります。
効率よく弦振動を受け取り上手く鳴り始めた響板は、弦と一緒に(周期の等しい2つの振り子が繋がったように)振動エネルギーを温存することによって、音の伸びを伴いながらながらゆっくりと減衰してゆくのです。
例えるならば、重心のバランスが取れていてよく飛ぶ紙飛行機が、風に乗って滑るようになだらかにゆっくりと下降してゆくようなイメージです。
弦から響板に与えられたエネルギーやその成分に過不足(アンバランス)があると、響板は弦とうまく連動して鳴ってくれません。
連動していない弦だけの音はやがて急速に減衰してしまうのです。
バランスが悪くうまく風に乗らない紙飛行機は、どんな投げ方をしても手元を離れた途端ストンと失速してしまうのと同じです。
これでは、二分音符や全音部など長く伸ばす音は楽譜に書いてある通り表現できません。
こもった音、よく鳴らない音というのは音色や音量の問題だけでなく「伸びない音」ということでもあり、演奏機能上の問題として質問者さまのフラストレーションにつながっているのではないかと思われます。
さて、エネルギーがロスしてしまう主な要因は、大きく2つに分けることが出来ます。
一つ目は私たち調律師が「整調」と呼んでいる鍵盤やアクションの調整整備状態の不備によるものです。
これらの調整に問題があると、摩擦や運動方向のブレ、運動効率の妨げとなって、鍵盤、アクションからハンマーが受け取り、そして弦に与えるべきエネルギーが十分に伝わりません。
アップライトピアノでしたら、調律のついでに最低限でも鍵盤を全て外して鍵盤の下に溜ったホコリなどを掃除機で吸い取り、鍵盤を支えているピンの汚れやくもりをベンジンやアルコールで拭き取ることが出来ます。
これだけでも、ピンの摩擦抵抗によりエネルギーを吸われていた鍵盤が、驚くほどスムースに動くようになり、多分「こもったような感じ」の何割かは改善すると思われます。
これも効果的で大事な「整調」の一例です。
二つ目は、ハンマーが弦に衝突する時に、ハンマーそのものが過度にエネルギーを吸収してしまっている場合です。
ハンマーの硬さや形状により、弦振動に与える成分や度合いが大きく変わり、響板への音の伝わり方も大きく変わります。
これらハンマーの形状や硬さの調整は「整音」と呼ばれていますが、ハンマーの形が潰れていたり、硬すぎても柔らか過ぎても響板が上手く鳴ってくれません。
以前に質問のあった硬化剤の問題は、ハンマーが「硬過ぎて」響板が上手に鳴っていない事例でしたが、柔らかすぎるハンマーも弦や響板に与えるべき音の成分を過度に吸収し、減衰の早い「鳴らない」ピアノの音になってしまうのです。
このように指からの力が、どこかで吸収されたり無駄になったりしないでハンマーに伝わった上で、そのハンマーが硬過ぎず柔らか過ぎず、ちょうど良い硬さに調整(整音)されていれば、よく飛ぶ紙飛行機の軌跡のような気持ちよく伸びやかな音でピアノは鳴ってくれるはずです。
どうすれば良いか、というご質問ですが、以上のような「鳴らないピアノ」の現状とその原因を正しく理解できて(「こんなものですよ」ではなく、何も言わなくても「これはお困りでしたね」と感じ取ってさっさと)手を動かしてくれる、つまり調律だけでなく整調や整音の重要性や本質ををしっかり理解し実践している調律師さんを探して依頼されることをお勧めします。
きっと見違えるように「豊かに伸びやかに鳴るピアノ」に生まれ変わると思います。
間違いなく整音の問題です

ピアノの森・調律工房
(埼玉県さいたま市浦和区)
森さん
間違いなく整音の問題です。
ユーザーの多くは、ピアノの音は調律で解決する、それで解決できなければ限界で買い替えるしかない、と思われているように思います。
実は、調律とは音の高さを合わせる作業で、音色調整は整音というまた別の作業があります。
しかし、この作業は調律のようにずれればまた元に戻せるというわけにはいかず、一回いじったものは基本元に戻りません。
作業の方法は、ハンマーフェルトに針を刺してフェルトを柔らかくしてピアノらしいポーンという音を作るのですが、刺す場所が悪いとモコモコとしたこもった音になります。こもりの原因は殆どがこれです。
改善方法ですが、先ほども申したように一回針を刺したものは元に戻りません。ですから、この刺した部分を削ることによって芯のある音が戻ってくるようになります。
しかし、そのままではキンキンとした硬い音なので、今度は正しい場所を刺すことによってピアノらしいポロンポロンという音を作り直します。多くのピアノがこの方法で改善します。
たまにフェルト深くまで間違った場所に針が刺されているハンマーもあり、この場合は新しいハンマーに交換するしかありません。
硬化剤を使うかたもおられますが、硬い音になるので私は使いません。硬化剤を塗った音とフェルトだけの音の区別がつかなければそれでも良いのですが、まず塗ったことはわかります。
削ったことでハンマーの形が悪くなっても、音が良くなればなにも気にならないはずです。
調律師が形が悪いことがよくないと不安を煽るのがよくないことでしょう。勿論、その原因を作ったのは悪い場所を刺した調律師です。
実際、間違った場所を刺されたことによるもった音は本当に多いです。でも、効率よく改善すれば、2時間もあればかなり音色が復活することが殆どです。
ピアノの音は変えられないと悩まれているかたも本当に多いのですが、正しい整音をすれば、それこそ別のピアノと思えるくらいに変わり復活します。
ぜひ一度ご相談いただけたらと思います。

「ピアノを習うと頭がよくなる」は、ほんとう? ピアノを習うことの良さ、メリットについて、ピアノ …